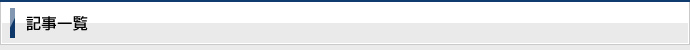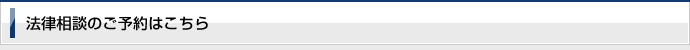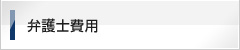【債務整理】 破産をしても返済しなければならない負債とは
札幌の弁護士による債務整理解説コラム第8回です。
前回(破産が認められない場合とは -免責不許可について)は、破産をしても債務の免除がされない場合を見てきました。
今回は、破産をして債務免除(免責)が認められても、免除されない負債について説明します。
破産を行って、免責が認められた場合、基本的にすべての債務が免除となり、一切返済する義務がないということをこれまで説明してきました。
しかし、特別に、破産を行っても免除されないもの、つまり、破産をしても返済をしなければならないものもあるのです。
このような、破産をしても返済義務が残る請求権を、非免責債権と呼んでいます。
非免責債権は、破産法253条に規定されており、以下のようなものがこれにあたります。
① 税金の支払い
滞納している税金や、今後請求が来る税金は、破産をしても免除されません。
免除されない税金には、所得税、住民税、固定資産税などのほか、健康保険や国民年金なども含まれます。
破産をしてもこれらの支払いは行わないとずっと義務が残ります。ただ、収入が少ない場合は、納税相談をすれば分割払いや一部免除が認められることもありますので、放置し続けないことが重要です。
② 悪意があって行った不法行為による損害賠償義務
悪質な違法行為で他人に損害を与えた場合、これを破産したからといって免除を認めては、あまりにも不公平となります。
そのため、悪質な場合に限り、破産をしても免除を認めないとしています。
③ 故意があるか、重大な過失によって、他人を死傷させた場合の損害賠償義務
たとえば、飲酒運転のために人をはねて怪我させたり死亡させたりしてしまった場合、その賠償義務は、破産をしても免除されません。
破産法では、被害者を保護するため、故意がある場合(わざと怪我させた場合)や重大な不注意によって他人を死傷させた場合には、破産をしても賠償をさせることとしています。
さきほどの②との違いが少しわかりづらいですが、たとえば、交通事故で他人を怪我させてしまった場合、普通は悪意があって事故を起こすのではなく、うっかり不注意によるものです。このような場合には②の「悪意がある」とはいえません。
他人に怪我をさせたり、死亡させてしまった場合に限って、被害者が賠償を受けられるように、悪意ある場合だけでなく、重大な不注意がある事故の場合などにも債務免除を認めないこととしているのです。
④ 婚姻費用(結婚中の生活費)や子どもの養育費
結婚中の生活費や子どもの養育費は、相手の生活を保障するためにも強く支払いが求められるため、特別に、破産による免除を認めないこととされています。
離婚の際の慰謝料はここでは保障されませんので、相手が破産した場合には免除の可能性があります(暴力や不倫の慰謝料は、②や③で保護される場合があります)。
⑤ 破産手続きの際に隠していた負債
破産手続きの場合には、一方的に債務免除を認めてもらう制度であるため、債権者(貸し手)には大きな影響を与えます。
そのため、債権者を必ず平等に扱い、一部だけを支払ったりすることは認められないとされています。
ところが、たとえば、自動車を残すためにローンを隠したり、クレジットカードを残すために1枚だけ隠していたりということがあります。
このように債務を隠していたまま破産を行った場合には、あとからやはり支払いができなくなったとしても、破産での免除が認められませんので、支払いを続けなければならなくなります。
破産手続きのルールに違反した以上、不利益を受けてもやむを得ないためです。
⑥ 罰金の支払い義務
事件を起こし、罰金の支払いを命じられた場合などは、破産をしても免除はされません。
ここに挙げたような負債は、破産を行っても免除が認められませんので、相手から支払いを請求された場合には、支払いを行わなければなりません。
ただ、税金や罰金以外の場合は、破産を行えば、実際には引き続き請求が来る例は多くありません。
免責が認められなくとも、破産申し立てを行うような状態では、支払いをするだけの財産がないことになりますので、相手もあきらめることが多いでしょう。
また、免除されない債務であることは、請求者側で証明しなければなりませんが、②や③の立証は実はそれほど簡単ではないからです。
ただし、免除されない以上、消滅時効が成立しない限り、一生負債が残ることになりますので、何年も請求され続ける可能性もあります。
いずれにしても、このような非免責債権があるかどうかは破産手続き上重要な問題ですので、早い段階で弁護士に説明する必要があるでしょう。
前回と今回は、免責がされない場合や免責がされない債務についてみてきました。
次回は、破産をした場合に退職をしなければならないのかという問題を取り上げます。
この点はよく依頼者の方から質問を受ける点で、関心が高いようですので、少し詳しく説明したいと思います。
札幌の弁護士が債務整理を解説 【債務整理に関する実践的情報一覧はこちら】
養育費が支払われない場合の対処法
札幌の弁護士による離婚解説コラム第10回です。
前回(養育費を受け取るには?相場はどのくらい?)の最後に予告しましたが、今回は、一度決めた養育費が支払われない場合を見て行きたいと思います。決めた養育費が支払えない場合、は次回に取り上げます。
では、さっそく本題ですが、養育費を取り決めたのに、支払われない場合、どうしたらよいでしょうか。
手紙や電話で催促をするのがもちろんですが、それでも支払いがされないことも、残念ながら何度も経験してきました。
養育費の支払いは期間が非常に長くなるため、途中で支払われなくなってしまうことも少なくないのです。
このような場合の対処法は、離婚が、協議離婚であった場合と、家庭裁判所での 調停離婚・裁判離婚であった場合とで大きく異なります。
まず先に、調停離婚・裁判離婚をし、その際に養育費の取り決めを裁判所で行った場合を見て行きます。
このような場合に相手が養育費の支払いをしなくなったときは、①家庭裁判所の履行勧告と、②強制執行、の2つの方法をとることができます。
①の履行勧告というのは、家庭裁判所の手続きで当事者がした約束について、約束違反があるときに、家庭裁判所が相手に事情などを確認し、約束通り支払いをするよう指示を出してくれるという制度です。
裁判所から、約束を守るようにと指示を受ければ、当事者が直接請求をした場合よりも、相手も支払いを行う可能性が高くなります。実際、履行勧告により支払いが再開されるケースもよく見かけます。
ただ、この履行勧告は、手軽で使いやすいというメリットはありますが、相手がそれに従わなくても何もペナルティはない、という点が弱点です。
履行勧告を行っても効果がない場合、あるいは最初から履行勧告が無駄と思われる場合には、②強制執行を行います。
強制執行というのは、裁判所の許可を得て、相手の財産を一方的に差し押さえてしまい、その財産を売却してお金に換え、そこから支払いを受けるという制度です。
強制執行を行うには、裁判所で当事者が合意した証明書である調停調書・和解調書や、裁判官の判断を示した判決書・審判書が必要です。そこに記載された約束が破られたときに、強制執行が認められます。
ただ、難しいのは、相手のどのような財産を差し押さえるかは、請求する側で決めなければならないのです。しかも、漠然と預金とか給料、というだけではダメで、北洋銀行の札幌西支店にある口座とか、○○株式会社からもらう給料、というふうに、内容を特定しなければなりません。
通常は、離婚前から相手の職場が変わっていなければ、その職場からの給料を差し押さえることが多いですね。残念ながら、相手が退職し、どこに勤めているかがわからないと、この方法は難しいでしょう。
給料以外にも、何か財産的価値があるものがわかれば、それを差し押さえることになります。
この差し押さえでも支払いを受けられないときは、もはや打つ手がなくなってしまいます。
相手に細かく督促を行うなどするしかありませんが、それで応じてもらえなければどうしようもないのが現実です。
養育費の支払いが確実に受けられるような制度があればいいのですが……
ここまでが、裁判所での調停離婚・裁判離婚をした場合です。
では、調停や裁判を起こさずに、協議離婚をし、その際に養育費を決めた場合はどうでしょうか。
実は、この場合、さきほどの履行勧告という手段は使えないのです。履行勧告は、裁判所が関与して取り決めた約束にしか利用できず、協議離婚の場合は対象外なのです。
では、強制執行はどうでしょうか。
この強制執行も、協議離婚の場合には、そのままでは利用できないことが多いのです。
さきほども触れましたが、強制執行には、調停調書や判決書という裁判所が作成した公文書が必要になります。協議離婚では、このような書類はありません。
ですので、基本的に強制執行は認められません。
しかし、だからといって打つ手がないわけではありません。
協議離婚で養育費を決めた場合であっても、あとから裁判所に、養育費の支払いを求める調停や審判を申し立てることが認められているのです。
ですので、このようなときは、養育費支払いの調停を家庭裁判所に申し立て、その中で相手と話し合いをしたり、裁判所に判断を出してもらうことになります。
そのようにして手続きが終了し、調停調書や審判書を裁判所に作成してもらった場合には、それを使って、履行勧告や強制執行を行うことができます。
協議離婚の場合には、トラブルになったときに改めて調停を行わなければならない、という点が不便ですし、時間もかかってしまいますから、なかなか大変な思いをしてしまいます。
そうすると、養育費が払われない可能性があるときは、協議離婚ではなく必ず調停離婚で決めなきゃ、と心配される方もいるでしょう。
しかし、協議離婚の場合にも、将来に備えた手段が1つ用意されています。
それが、公正証書です。
公正証書とは、公証人という特別な資格を持つ公務員が、公的に作成する証明書のことです。
当事者が取り決めた離婚や養育費に関する約束を、公証人の前で確認し、公証人がその約束事を公正証書に記載します。
そうして、公証人が公正証書に約束を記載したときは、この公正証書は、裁判所の調停調書や判決と同じ扱いを受けられる、という仕組みになっています。
ですので、協議離婚の場合には公正証書を作成しておくことで、いざというときに、調停や裁判を起こさずに強制執行を行うことができ、スピーディに解決を図ることができるのです。
そのため、弁護士が交渉して協議離婚する場合には、ほとんどの場合、この公正証書を作成しておきます。
ただし、この公正証書は、強制執行を行うことはできますが、家庭裁判所が関わっていないことにかわりはないので、履行勧告は認められません。
いきなり強制執行をするしかないのです。
普通は事前に請求書や督促を行いますので、大きな違いはないですが、その点が調停離婚・裁判離婚と、公正証書の違いでしょう。
少し複雑だったでしょうか。簡単に内容を整理すると、養育費が支払わない場合の解決方法は、
- 【協議離婚で公正証書なし】
支払いの請求 → 養育費の調停 → 解決 → 履行勧告 → 強制執行 - 【協議離婚で公正証書あり】
支払いの請求 → 強制執行 (履行勧告はできない) - 【調停離婚・裁判離婚】
支払いの請求 → 履行勧告 → 強制執行
という流れです。なお、支払いの請求や履行勧告は、省略することも可能です。
今回は思ったよりも長くなってしまいましたので、養育費を支払えなくなってしまった場合については、次回にまわしたいと思います。
札幌の弁護士が離婚を解説 【離婚に関する実践的情報一覧はこちら】
【刑事事件】 保釈を認めてもらう方法・手続きは?
札幌の弁護士による刑事事件解説コラム第5回です。
前回(保釈って何?)にひきつづいて、今回は保釈を認めてもらうための方法、保釈の手続きについてみていきます。
保釈の手続き自体は、非常にシンプルです。
ポイントを示すと、以下の3つだけです。
- 起訴されたあと、判決が出るまでの間に、
- 裁判所に保釈請求書を提出し、
- 保釈の許可が出たら保釈金を裁判所に納める
保釈を求める手続きとしては、この程度です。
ここで保釈のためのハードルは、2つです。
1つは、裁判所に保釈を許可してもらうこと。もう1つは、保釈金を用意することです。
保釈の許可を受けるためには細かい条件がいくつがありますが、前回もみたとおり、主に問題となるのは、保釈を認めた場合に「証拠隠滅」と「逃亡」の危険がないかという点です。
ですので、弁護士が保釈の請求をする場合、証拠隠滅の危険も逃亡のおそれもないことを可能な限り主張立証し、裁判官を説得するのです。
では、それをどうやって説得するかという点ですが、それは個々の事件ごとにポイントが異なりますので、一概にはいえません。
ただ、保釈を求める場合にはまず行うことが1つあります。
それは、身元引受人を立てるということです。
保釈の申請をする際に、家族などの身元引受人に協力してもらい、裁判所にあてて、「保釈された場合には、私が責任を持って監督します」というような書面を作成してもらうのです。
これを行うことで、被告人には一応心配して協力してくれる人がおり、被告人もそれを簡単には裏切らないだろうと考えるなど、裁判所が保釈を認める事情の1つになります。
そして、たいていは、保釈金を用意してもらう人に、そのまま身元引受人をお願いしています。保釈金を出すほど被告人と関係が深い方であれば、まさに身元引受人として適任といえるでしょう。
では、身元引受人になったものの、被告人が保釈後に問題を起こしてしまった場合、身元引受人も何か責任を負うのでしょうか。
実は、そのような心配はいらないのです。身元引受人は、裁判所との約束のようなものではありますが、これに違反をしても何かペナルティがある、ということはありません。
ですので、身元引受人になったからといって、何か責任を負ったり、損害の賠償を求められたりということもありません。
ただ、当然、裁判所との約束ではありますので、できるだけ守ることが求められるでしょう。
なお、身元引受人がいないと保釈がまったく認められないかというと、そういうわけでもありません。
いた方が望ましいとはいえますが、いなくても保釈が認められることはいくらでもあります。
ですので、身元引受人になる方がいなくとも、保釈をあきらめる必要はありません。
ともかく、保釈の際には、身元引受書などの資料があればそれも添付して、裁判所に保釈の申請書を提出します。
申請書の作成は、保釈の請求に慣れている弁護士であれば、正直、1~2時間もあれば十分です(もちろん、事件の内容を把握していればですが)。
申請書を作成したら、資料とともに裁判所に提出します。
裁判所は保釈の申請書を受け取ったあと、必ず、担当検察官に保釈についての意見を聞きます。
検察官は、保釈には強く反対するとか、保釈をしてもかまわないとか、事件ごとに意見を出します。
その検察官の意見が裁判所に出たあと、裁判官が保釈の判断を行います。
札幌地裁で保釈の申請を行う場合、検察官の意見が出てくるのがだいたい申請の翌日になります。
しかも、土日は基本的に手続きが動きませんので、たとえば金曜日に保釈の申請をすると、判断が出るのが月曜日になることが通常です。
地域によってはその日のうちに判断が出るところもあるようですが、私の経験上、札幌ではたいてい翌日ですね。
これまで何件も保釈請求をしていますが、当日中に判断が出た経験はなかったように思います。
そうして裁判所の判断が出ることになりますが、裁判所の判断は、「許可」か「却下」の2パターンです。
「許可」の場合は、同時に、保釈金の金額と、保釈時に守るべき条件が指定されます。
その条件を守らないと、保釈金が没収され、保釈が取り消しとなってしまうのですが、その条件については次回以降に取り上げたいと思います。
保釈が許可されればあとは保釈金を納めるだけですが、反対に、保釈が「却下」されてしまうこともあります。
却下の場合は、保釈が認められなかったことになりますので、これに対して異議申し立てを行うかを検討することになります。
異議申し立てをしても保釈が認められなかった場合や、異議申し立てを見送った場合、もう保釈が認められないかというと、そうとは限りません。
保釈請求は、判決が出るまではいつでも、何度でも、することができるのです。
一般に、裁判の審理が進み、証拠や証人が取り調べられていくにつれて、証拠隠滅の危険は減っていきます。一度裁判所に提出された証拠をあとから隠滅することは難しいからです。
ですので、起訴された直後に保釈が認められなかったとしても、裁判を何度か重ねた段階で改めて保釈請求をすれば、今度は認められることもあります。
私の経験上では、保釈請求が4回却下され、5回目でやっと認められたケースもありました。
とはいえ、保釈が却下されたあと、すぐにまた申請をしてもまったく意味はありません。
あらたに保釈請求をするには、新しい資料が入手できた場合や、裁判がある程度進展し、状況が多少なりとも変化したといえることが必要です。
そういった事情もないのに保釈請求を繰り返しても、裁判所はまともに取り合わないでしょう。
さきほど述べた5回目で保釈が認められた件は、最初の保釈申請から最後の保釈申請までは、1年以上が経過していました。
保釈が許可され、保釈金を納付すれば、その直後に釈放され、自宅に帰ることができます。
自宅に帰ったあとは、保釈時の条件さえ守れば、あとはどのように生活をしても問題ありません。
仕事をしても良いですし、条件を守れば、旅行などにも行けます。
ただ、裁判には必ず出席する必要があり、判決が出た時点で、保釈も終わりになります。
判決が無罪や執行猶予判決ならそのまま自宅に帰ることができますが、実刑判決であれば、その場で身柄拘束されてしまうことになります。
以上が、保釈の手続きの流れです。
保釈制度には複雑なところもあり、誤解も多い制度です。ただ、やはり身柄拘束された被告人にとっては、特に強い関心があるところだと思います。
次回以降も、引き続き、保釈をテーマとしていきたいと思います。
札幌の弁護士が刑事事件を解説 【刑事事件に関する情報一覧はこちら】
【債務整理】 破産が認められない場合とは -免責不許可について
札幌の弁護士による債務整理解説コラム第7回です。
前回(破産すると住宅はどうなる?すぐに出ていかないとならないの?)は、破産した際の住宅の取扱いについて取り上げました。
今回は、破産の申立てをしても、債務の免除が認められない場合についてです。
破産状態であったとしても、必ず破産手続きをとれば債務がなくなるというわけではありません。
債務の免除を受けるには、裁判所から「免責」(支払責任を免除すること)の許可を得なければならないのです。
破産は、債権者の同意もなく、一方的に債務をすべてゼロにしてしまう手続きであり、非常に強力です。
そのため、あまりにも不誠実な理由で借金を作ったり、破産を行おうとする人にまで免責を認めるべきではないと考えられています。
破産法では、そのような不誠実な事情のある一定の場合には、免責を認めないと規定しています。
それでは、どのような場合が免責不許可になるのでしょうか。破産法252条では、11項目の事情が挙げられていますが、主に問題となるものを見て行きます。
① 財産隠し
破産手続きを行う場合には、一定以上の価値のある財産を売却・処分し、代金を債権者への配当にまわさなければなりません。
しかし、中には、債務の免除は受けたいけれども、財産は手元に残したいと考えて、預貯金を親族に口座に移したり、車を隠し持ったりする場合があります。
このような財産隠しは、破産法の基本的なルールに違反し、極めて不誠実といえるため、これが発覚したときは免責を認めないとされています。
② 一部の債権者のみにあえて支払いをすること
破産手続きでは、債務がすべて免除になるかわりに、一部の債務のみの支払いを行うことも認められていません。
一部だけ支払い、それ以外は一切支払いをしなくてよいとすると、債権者にとって不公平となってしまうからです。
たとえば、車を残すためにローンだけ払う場合や、保証人がついた負債だけを支払うということも認められていません。
このようなルール違反は、ほかの債権者への裏切り行為になるため、免責不許可の事情とされています。
③ 浪費、賭博
浪費やギャンブルによって、多額の借金をした場合です。
多少の無駄遣いやギャンブルは問題にはなりませんが、度が過ぎており、正常な生活をおびやかすようなものであれば、免責不許可の事情になります。
たとえば、支払いができないことがわかっていながら、自動車や高級化粧品を買い続ける行為や、借金が返せないのに月に5万円もパチンコにつぎこんだような場合です。
借金の事情事態が不誠実で、破産を認めて救済すべきでないと判断されると、免責不許可となります。
④ 破産することをわかっていながら借金をした場合
破産をして免責が認められれば、負債を返済する必要はなくなります。
これを悪用して、破産直前にカードなどをできるだけ使い、最後に借金をする人も残念ながら見かけます。
しかし、破産をして免除してもらうつもりなのに、借入れを行うことは、立派な詐欺行為になり、逮捕されてもおかしくない行為です。
当然、そのような違法行為をあえて行った者を免責により救済すべきではないため、免責不許可となります。
⑤ 裁判所や破産管財人の調査を拒否したり、嘘をつくこと
裁判所や破産管財人は、破産手続きを適切に行うために、さまざまな調査をします。その中で、破産を申し立てた方に事情を聞く機会もあります。
その際に、嘘をついて財産を隠したり、都合の悪いことをごまかす人や、めんどくさいという理由で一切調査に応じない方もまれにいます。
しかし、自分で破産を希望しておきながら、裁判所の調査にまじめに応じないというのでは、破産免責を認める必要はありません。
そのため、このような場合も免責が認められません。
⑥ 免責から7年以内に新たに破産を申し立てる場合
実は、破産は人生に一度切り、というわけではなく、何度でも破産を認めてもらうことは可能とされています。破産に回数制限はないのです。
しかし、短期間に何度も破産を繰り返されては、債権者も納得できませんし、本人もどうせ破産すれば良いと不誠実な対応をしかねません。
そこで、一度破産をしてから7年以内に限り、破産免責を認めないとされています。
特に、前回の破産時の反省を活かせないで、同じような理由で借金を重ねた場合には、認められない可能性が非常に高くなります。
よく問題となる免責不許可の事情はこのようなものです。
しかし、注意が必要なのは、これらの事情があるからといって、必ず免責が認められないわけではないということです。
これらにあたる場合でも、その程度が軽い場合とか、やむを得ない事情がある場合、またはよく反省している場合などには、裁判所が特別に免責を許可してくれることもあります。
実際上は、免責不許可の事情はあるけれども、さまざまな事情を考慮して免責を認めます、という決定は非常に多く見かけます。
もちろん、これらの事情はない方がスムーズに免責が認められますが、そのような事情があったとしても、適切な対処を行っていけば免責が認められる可能性は決して低くはないのです。
破産の最終的な目標は免責を得ることですので、免責にならなければ、破産を申し立てた意味はほとんどなくなってしまいます。
免責は必ず認められるわけではありませんので、免責不許可の事情がないかを検討し、もしあてはまる場合にはしっかりと対処をすることが必要です。
破産の依頼を受ける場合に、弁護士がもっとも注意する点の1つですね。
今回は免責が全く認められない場合がある、という点を見てきました。
しかし、実は、免責は認められたのに、一部の債務が残ってしまうという場合があるのです。
次回は、そのような免責の対象とならない債務について取り上げます。
札幌の弁護士が債務整理を解説 【債務整理に関する実践的情報一覧はこちら】
【刑事事件】 保釈って何?
札幌の弁護士による刑事事件解説コラム第4回です。
前回(裁判・公判の流れや注意点を確認しよう)では、起訴された場合の裁判の具体的な流れを見てきました。
今回のテーマは、「保釈」という制度です。
ニュースなどで耳にする機会の多い言葉ですが、実際には、誤解されている方が非常に多いといえます。
「お金持ちはお金を出せば出してもらえる」「お金を払って保釈されるなんて、反省していない」と理解してはいないでしょうか。
保釈というのは、意外と奥が深い制度なのです。
逮捕され、身柄拘束されている人が起訴された場合、裁判を受けなければなりません。
起訴されてから判決が出るまでは、早くて1ケ月、通常で2,3カ月以内ですが、少し複雑な事件になると1年を超えることもあります。
前にも見てきましたが、身柄拘束された状態から起訴された場合、判決までの間、ずっと身柄拘束が続いてしまうことになります。
裁判が終わるまで、釈放されることはないのです。
しかし、よく考えてみれば不思議な制度です。
逮捕・起訴された人の中には、一部ではありますが、無罪となる人も含まれています。
そのような人であっても、起訴された場合、そのまま判決までの長期間、留置場・拘置所で身柄拘束されなければなりません。
また、比較的軽微な事件で、執行猶予判決が確実である場合なども、判決が出るまで釈放されないことになります。
しかも、このような判決までの間にかかる時間というのは、裁判官、検察官、弁護人が裁判の準備をするための時間です。
裁判所も検察官も弁護人も、たくさんの事件を抱えているため、裁判を早く進めようとしても、どうしても1ケ月に1回程度のペースでしか進みません。
検察官の準備が遅かったり、裁判所が多忙であったりして裁判が長引いたとしても、被告人はそのまま身柄拘束を受け続けたままになります(実は、お盆や年末年始などを挟むと、休暇などのため裁判が長引きます)。
そのうえ、判決でたとえば懲役3年の刑になった場合、刑期はその判決後から計算します。
その判決までの間に1年間身柄拘束をされていても、その1年分をそのままひいてもらえるわけではありません。
裁判所の判断で、一定の期間分を刑期から差し引いてもらうことは認められていますが、それでも差し引いてもらえない日数は相当なものとなります。
判決が決まるまでの被告人は、留置場や拘置所で、労働などが与えられるわけでもなく、ただ、朝から夜まで部屋に座って時間を過ごすだけです。
本当であれば、起訴された後は釈放して、自宅から裁判に出席させ、実刑判決が確定すれば服役させれば十分ではないでしょうか。
では、どうしてそのような制度でなく、身柄拘束が続けられるかといえば、「証拠隠滅」や「逃亡」を防止し、裁判を適正に行うためなのです。
裁判が始まる前の段階では、自分の刑を軽くしたり、ごまかすために、重要な証拠を隠したり、関係者に口裏合わせを行う者がいないとも限りません。
また、重い刑が予想される場合には、裁判に出席せず、行方をくらましてしまう危険があります。
このような事態を防止するために、裁判が終了するまで釈放しない扱いとされているのです。
これは、反対にいえば、そのような証拠隠滅や逃亡の危険がないのであれば、身柄拘束する必要性はないことになります。
実刑判決後の服役は、事件に対する制裁などの意味合いがありますが、判決確定前の身柄拘束は、無罪が推定された状態ですので、制裁としての意味は薄いでしょう。
そのように、証拠隠滅や逃亡のおそれがない者を釈放し、自宅から裁判に出席することを認める制度が、保釈なのです。
ですので、お金を持っているとか貧しいとかいう事情は関係なく、反省している、していないということとも関係がありません。
単に、裁判を正常に進めるためには身柄拘束を続けるべきか、釈放しても問題ないか、という観点が保釈においては重要なのです。
起訴され、裁判にかけられる人の中には、逮捕をされないまま起訴され、自宅から裁判に出席する人も多くいます。
それに対し、一度逮捕され、そのまま起訴された人は、判決まで釈放が認められないというのは釈然としません。
そのため、特に必要性がない場合には釈放を認め、自宅から裁判に出席させれば十分です。
それが、保釈という制度が認められる理由です。
そうすると、裁判所が保釈を許可したということは、裁判所が、「その人を拘束しておく必要はないし、釈放してもそれほど問題がないだろう」と認めたことになります。
報道などで被告人が保釈請求をしたことや、保釈されたことを非難するような意見を見聞きすることもありますが、これまで見てきたような保釈という制度を正しく理解されていないのだと思います。
保釈しても問題がない事件では、積極的に保釈を求めるのが本来だと考えていますので、私も本人の希望があったり、身柄拘束の必要がないと思った場合には、すぐに保釈請求を行っています。
これまで、保釈された被告人が何か問題を起こした経験もなく、すべてとどこおりなく裁判が終わっています。
保釈を受けた被告人は、一定の条件はつきますが、釈放されて自宅に戻り、もとどおり自由に生活をすることが認められます。
仕事をしたり、外出したりすることも問題なく認められています。
一定の条件を守ることと、裁判に必ず出席しさえすれば、普通どおりに生活して構いません。
その状態が、判決の日まで続くことになります。
ここまで保釈とはなにか、を見てきましたが、少しわかりづらかったかもしれません。
ただ、刑事裁判では、裁判所も弁護人も、保釈の請求をすることは正当な権利だと考えており、保釈請求をしたことで、裁判所が不快に思うとか、反省していないと判断するということは絶対にありません。
そのような理由で保釈をためらう必要はないのです。その点は特に理解していただければと思います。
少し長くなりましたので、どうすれば保釈が認められるのか、については次回にしたいと思います。
札幌の弁護士が刑事事件を解説 【刑事事件に関する情報一覧はこちら】
養育費を受け取るには?相場はどのくらい?
札幌の弁護士による離婚解説コラム第9回です。
前回は、「必ず母親が親権を得る? - 親権者の決め方は」というテーマで、親権者の決め方を見てきました。
親権が決まり、子どもを育てることになると、今度は他方の親から養育費を受け取れるのかが問題になります。
養育費を受け取る条件や、その金額はどの程度になるのか、を今回は取り上げます。
実は、法律上、養育費という言葉は出てきません。
民法766条で、「子の監護に要する費用の分担」は、子の利益を最も優先して考慮し、夫婦間の協議で定める、という規定があるだけです。
一応、この「子の監護に要する費用」が養育費にあたると考えられるでしょう。
しかし、具体的な金額などについては何も触れられていないため、どのように決めるべきか悩むケースが多いと思います。
基本的には、夫婦間の協議で決めますので、双方の合意が成立すれば、いつからいつまで支払うことにしても、一括でも分割でも、金額もいくらでも構わないことになります。
協議で決める場合の注意事項については次回に取り上げる予定ですが、いずれにしても協議で決まれば問題はありません。
では、協議が整わない場合、あるいは離婚や親権自体に争いがあり、養育費を決めるどころではないという場合にはどうしたらよいのでしょうか。
このような場合、離婚の場合と同様、やはり調停を申し立てることになります。
離婚についても未解決のときは、離婚調停の際にあわせて養育費の請求も行うことができますし、反対に離婚が成立した後、養育費の取り決めができていなかった場合は、子どもが成人するころまではいつでも調停を申し立てることができます。離婚時に決めなかったから請求できない、ということはありません。
調停で合意できなかった場合は、最終的には判決や審判という形で、裁判所の判断が示され、当事者がそれに拘束されることになります。
では、実際に養育費を決定する際、期間や金額はどのようになるのでしょうか。
まず、養育費の支払い期間というのは、離婚が確定した日から始まります。離婚前の時点では、養育費という形での支払いは認められていません。ただし、生活費として婚姻費用というものの支払いが認められることになります。
離婚後、いつまで養育費の支払義務が続くかですが、通常は、20歳になって成人するまでで区切ることになります。20歳になれば親権もなくなりますので、その成人したら養育費の支払いも不要と扱われます。
しかし、実際に協議や調停で決定する際には、少し異なる決め方をすることも少なくありません。
たとえば、子どもが高校を卒業すると同時に就職するような場合、仕事をして収入のある子に対してまで養育費を変わらず支払うべきといえるかは微妙な問題だと思います。反対に、高校卒業後に大学に入学した場合、20歳ではいまだ学生で、学費も相当かかる状況ですから、20歳になったからといって養育費を打ち切るというのも違和感があります。
ですので、たとえば、「大学に進学したときは大学卒業まで、大学に進学しなかったときは20歳まで」などという形で合意することもあります。
実際には、浪人してしまった場合や中退した場合はどうするかで問題になることもありますが、あまり細かいところまで決めておくよりは、そのときに話し合う方が現実的といえる場合もあるでしょう。
※ただし、法改正のため、2022年4月以降は、成人年齢は18歳に変更されます。その後の養育費の支払時期がどうなるかは、今後議論されていくこととなります。
では、肝心の金額はどのように決めるのでしょうか。
基本的な考え方として、養育費は、父母の収入額に応じて決定されます。
通常、父母の収入から子どもの生活費を見積って、その子どもの生活費を父母が収入に応じて分担する、という形で計算します。
そうすると、母が子どもを養育し、父が養育費を支払う場合では、父の収入が大きいほど養育費は高くなり、反対に、母の収入が高いほど受け取る養育費は低くなります。
また、子ども数や年齢、親が自営業者か会社員かなどによっても養育費の額が変動していきます。
ただ、これらの要素をもとに計算をしていくと計算が大変複雑になり、わかりづらくなってしまうため、実際の裁判では、養育費の目安を整理した算定表を使用しています。
この表は、両親の収入、子どもの数、年齢から簡単に養育費の目安が算定できるため、実際の事件でもよく参照されます。
東京家庭裁判所のサイトに算定表が掲載されていますので、興味ある方はこちらをご確認ください。
この算定表は、標準的な家庭を基準として、目安を決めたものですので、どんな場合にもこのとおりに決定されるというわけではありません。
実際には、個々の家庭ごとに経済的な事情が異なります。子どもが学費の高い私立の学校に通う場合などの子どもの生活費が高くなる場合や、住宅ローン、親の介護費など特殊な支出を一方の親がしている場合などは、算定表から増減することもあり得ます。
そのため、この算定表は絶対的なものではありませんが、実務上は、だいたいの事案はこれに沿って協議を進めることになります。
養育費は、調停や裁判ではこのような流れで決めていきますが、非常に長い期間、支払いが続くことになりますので、基本的には当事者が納得して合意しなければ、途中で支払いがされなくなってしまう危険が高まります。
また、当事者で納得して決めたとしても、養育費の支払期間は長く、その間にお互いの生活状況が変わってしまうこともありますので、既に決めた養育費では足りないとか、高すぎるとかいう事態が生じたり、全く払われなくなってしまうということも起きてしまいます。
このように、養育費を決めた後に問題が生じた場合にどうしたらよいか、という問題は、次回に取り扱いたいと思います。
札幌の弁護士が離婚を解説 【離婚に関する実践的情報一覧はこちら】
【刑事事件】 裁判・公判の流れや注意点を確認しよう
札幌の弁護士による刑事事件解説コラム第3回です。
前回(刑事事件の流れ(後)~起訴から判決まで~)までで、刑事裁判のおおまなか流れを見てきました。
今回は、肝心の裁判(公判)でどのようなことを行うのかを実例をベースに見て行きたいと思います。
1 裁判所への出頭
刑事裁判の第一審は、地方裁判所の場合と簡易裁判所の場合があります。
札幌では、札幌地方裁判所と札幌簡易裁判所の建物が別々になっていますので、注意が必要です。
被告人には裁判所からの公判期日の通知書が届いているはずですので、その日時に指定された法廷に出頭します。
なお、身柄拘束中の被告人は、拘置所から送迎されますので時間や場所を間違う心配はありません。
2 公判の開廷
時間になると、公判が始まります。
法廷には必ず傍聴席があり、事件と関係ある方も関係ない方も、自由に傍聴できます。出入りも自由です。
最近は裁判員裁判などで刑事裁判が関心をひいているためか、札幌地裁でのだいたいの公判には傍聴人が3,4人程度は来ています。
ときどき、学生や職場ごとの集団傍聴が行われることがあり、傍聴席が満席になることもありますが、気にしないでもらうしかありません。
ちなみに、傍聴券が発行されるのはごく一部の著名事件だけで、普通の裁判ではそのようなことはありません。
法廷の中には、検察官と弁護人が、法廷の左右にわかれて、それぞれの席につきます。法廷のイメージは、だいたいテレビドラマやニュースで見かけるとおり、正面に高い壇がもうけられており、そこに裁判官が座ります。
被告人は、弁護人席の前にある長イスにかけるか、裁判官の正面に、傍聴席に背中を向ける形で座る場合の2通りがあります。
ちなみに、最近、裁判員裁判などでは弁護人の隣に着席できるケースも見られるようになってきました。
裁判官は、大半の事件では1人のみです。ただし、重大事件や複雑な事件では裁判官が3人になることもあります。
3 裁判官の入廷
法廷に被告人、弁護人、検察官が集まり、時間になると裁判官が法廷の奥から入廷し、裁判官席に着席します。
そこから公判が始まります。
裁判官が入廷すると傍聴人も含めて全員が起立し、裁判官が着席前に一礼するのにあわせて、全員で一礼します。
ちなみに、これは裁判官や特定の人に礼をしているというよりは、法廷やこれから始まる裁判に向けて、一礼しているという意識が強いと思います。
4 人定質問(本人確認)
法廷が始まると、まず、被告人が法廷中央の証言台前に立つよう指示されます。
そこに立つと、裁判官から、人定質問(じんていしつもん)という手続きが行われます。簡単にいえば、本人確認です。
聞かれるのは、氏名、本籍、住所、生年月日、職業で、聞かれたとおりに答えるだけです。
よく本籍がわからなくて戸惑う方がいますが、覚えてなければ裁判官が「○○でいいですか」と確認してくれます。
ただ、答えられないと緊張してしまう方も多いので、私は、事前に起訴状に記載してある本籍・住所等を確認してもらっています。
5 罪状認否
人定質問が終わると、いわゆる罪状認否が行われます。
まず、検察官が、起訴状に記載された事件の内容を読み上げます。起訴状の記載はシンプルなもので、「被告人は、○月○日、○○区○○のスーパーから、○○を盗んだものである」というような必要最小限の情報だけです。
検察官が起訴状を読み上げた後、裁判官から被告人に対して、黙秘権の説明が行われます。
そして、起訴状に記載された内容に間違っているところはないか、要するに被告人が本当にそれを行ったのかなどを裁判官から質問されます。
間違いがなければ、「間違いありません。そのとおりです」と答えますし、違っていれば、「私はそのようなことはしていません」というように答えます。
その時点で、この事件が犯行を認めている自白事件なのか、犯行を否定している否認事件なのかが確定します。
これが終わると、被告人は元の席に着席するよう指示され、しばらく座って裁判の様子を見ているだけになります。
6 冒頭陳述
罪状認否がおわると、検察官から「冒頭陳述」(ぼうとうちんじゅつ)が行われます。
これは、今回の事件がどういう流れで起きたのか、どういう被害があったのかを具体的に説明するものです。
起訴状朗読では必要最小限の情報しか記載されず、事件の動機や背景などはわかりませんので、この冒頭陳述で内容を明らかにしていきます。
なお、注意が必要なのは、この冒頭陳述は、検察官側から見た事件の説明でしかないということです。つまり、検察官の考えはこうだ、というものです。
ですので、被告人の言い分はこれと違う可能性はありますし、裁判所の考えも異なる可能性もあります。
検察官側の見立てを説明するのが冒頭陳述という手続きです。
これが終わった後、弁護人や被告人が反論をすると思われる方もいるかと思いますが、実は大半の事件では、弁護人や被告人が冒頭陳述を行うことはありません。
複雑な否認事件や裁判員裁判になっている事件では、弁護人も対抗して冒頭陳述を行うことがありますが(裁判員裁判では必ず行います)、それ以外の事件では冒頭陳述を行わないことが普通です。
これは、被告人の犯行を証明する義務は検察官にあり、弁護人や被告人が、積極的に意見を述べたり、無罪を証明する必要がないとされていることと関係しています。
ただ、実際は、通常の自白事件では冒頭陳述を行わなくても裁判官は理解できるだろう、という考えがあるから、あえて弁護人が冒頭陳述まで行っていないのでしょう(なお、検察官は、法律上、必ず冒頭陳述を行う義務があります)。
7 検察官の立証
冒頭陳述は検察官の言い分ですので、それだけでは何も証明されたことになりません。
ですので、冒頭陳述が終わった後、検察官は、事件の内容を立証・証明していきます。
証明といっても、ほとんどは、捜査資料の要約を読み上げるだけで、証人尋問などを行う事件は一部に限られています。
通常の自白事件であれば、その読み上げも5分から10分程度で行われています。
しかし、否認事件であれば、検察官も多数の証人尋問を実施することもあり、その尋問を行うために日を変えて何度も公判を実施することになります。
8 弁護側の立証
検察官の立証が終わると、今度は弁護人・被告人側からの立証が行われます。
自白事件であれば、被告人の刑の重さが問題となりますので、被告人が事件後に深く反省してきたことや、家族が監督していくこと、被害者に弁償し示談が成立していることなどを立証する必要があります。
そのために関係書類を提出するほか、家族や被告人自身の尋問を行うことになります。
家族と被告人が証言台に立つときは、通常、家族から証言を行い、被告人は最後になります。
事前に弁護人と打合せをしてから公判にのぞむことになりますので、証言の際も、何をいっていいか全くわからないということは少ないと思いますが、特に被告人質問は刑事裁判の山場ですので、よく準備し、言いたいことを明確に裁判官に伝える必要があります。
弁護側の証人尋問、被告人質問が終了すると、審理はほぼ終了です。
9 論告・弁論
お互いの立証が終了した後、検察官が、「論告」(ろんこく)を行います。
これは、検察官が審理の内容を踏まえて、どのような判決をすべきかを主張するものです。「○○という証拠があり、○○という事情があるから、被告人を有罪にして、懲役○年の刑を科すべきである」、という内容になります。
冒頭陳述と内容は似通ってくることもありますが、懲役○年にすべき、という「求刑」が行われる点が特徴です。
これに対し、弁護人からは、「弁論」(テレビなどでは「最終弁論」という言い方が多いですね)を行います。これは、検察官の論告に対抗して、弁護人として適切な判決はこうあるべきだという意見を主張する場です。「○○という証拠からすると、被告人の犯行は立証されておらず、無罪だ」「○○という事情があるから、被告人には執行猶予付きの判決で十分である」というのが弁論です。
10 被告人の意見陳述
審理の一番最後には、被告人が再び証言台に立ちます。
裁判官から、「これで審理を終えますが、最後に何か言いたいことはありますか」と質問されます。被告人に、言い残したことや、一番伝えたいことを話す最後のチャンスを与えるためのものです。
ただ、その直前に被告人質問で十分話したいことを話していることも多く、「特に付け加えることはありません」という内容で終わってしまう例もみかけますが、私は、事前に打ち合わせをして、必ず何か話してもらうことにしています。
傍聴席にいる家族への言葉だったり、被害者への謝罪だったり、今後に向けての決意など、内容はさまざまですが、裁判の終わりに際して何も言うことがないというのでは、どうしても物足りない感じがしてしまうからです。
なお、重大事件や否認事件では、意見陳述を何十分も、場合によっては1時間以上することもありますが、自白事件では本当に一言、二言で終えることが通常でしょう。
被告人の陳述が終わると、判決の言い渡し日時を裁判官が指定し、その日は終了します。
11 判決言い渡し
指定された判決公判で、裁判官から、判決の結論と理由が宣告され、第一審は終了となります。
内容に応じ、控訴するかどうかを検討することになりますが、控訴をしないのであれば、そこで刑事裁判は終わりです。
控訴する場合には、控訴の手続きを行い、高等裁判所で第二審が実施されることになります。
以上が、刑事裁判の実際の流れです。
これが通常の自白事件であれば、1時間以内、1回の裁判で実施されることがほとんどでしょう。
裁判員裁判などではもう少し時間をかけますが、流れはほとんど変わりません。
このような、裁判のそれぞれの場面でどのように対応していくかは、弁護士と被告人が十分に打合せをして、しっかりと決めておく必要があります。
次回は、裁判の途中で釈放をしてもらう保釈という手続きを詳しく見て行きたいと思います。
保釈は、非常に誤解されやすい制度ですので、正確な知識を確認していただければと思います。
札幌の弁護士が刑事事件を解説 【刑事事件に関する情報一覧はこちら】
【債務整理】 破産すると住宅はどうなる?すぐに出ていかないとならないの?
札幌の弁護士による債務整理解説コラム第6回です。
前回は「破産をすると、家族や職場に迷惑がかかる?」という問題を見てきましたが、今回は、住宅ローンがある場合の破産についてです。
住宅ローンは、債務整理を検討するうえでもっとも重要な問題となります。
ご相談に来る方も、やはり自宅がどうなるかといった点に関心が高い場合が多く、住宅をなんとか残したいと希望される方は非常に多いといえます。
そこで、破産をする場合の住宅がどうなるか、出ていかなければならないかという点を取り上げていきます。
まず、結論からいえば、破産を行う場合には住宅を手放すしかありません。住宅を維持したまま、破産を行うことは認められないのです。
これには、2つの理由があります。
1つは、これまでも見てきたように、破産を行う場合、財産を処分しなければならないからです。一定以上の価値のある財産は、売却するなどしてお金に替え、債権者に分配しなければなりません。
不動産は、売却したときの金額よりも、住宅ローンの残額が少ない場合、その差額が資産とみなされます。たとえば、売却すれば2000万円、住宅ローンが現在1500万円残っている不動産は、差額の500万円分の価値があるとみなされますので、これを売却して500万円を債権者に分配するのです。
ですので、住宅ローンをある程度返済し、ローン残額が少ない場合は、処分しなければならないのです。
では、住宅ローンの残額が多く、売却してもローンが残ってしまう場合はどうでしょうか。たとえば、住宅を売却しても1000万円にしかならないのに、ローンが1300万円残っている場合です。
この場合、この住宅を売却してもすべてローンにあてられますので、実際には価値のない財産とみなされます。
ですので、これを売却して売却代金を分配することはできません。
ところが、この場合もやはり住宅を残すことはできないのです。
その理由が、破産を行う場合には、一部の債権者への返済を続けることが許されない、というものです。
破産は、すべての債務を一気に免除してもらうという非常に強力な制度ですが、そのかわり、すべての債権者を平等に扱う必要があります。ですので、一部の債務のみを返済することは禁止されています。
そのため、住宅ローンのみを返済してくことも認められないのです。
ローンが返済できない以上、住宅は競売にかけられることになり、結局、追い出されてしまうのです。
この2つの理由で住宅を手放さなければなりませんが、この2つのどちらにあたるかで、実際の処理は少し変わってきます。
住宅を売却しても代金が残り、債権者へ分配する場合は、住宅の売却や債権者への分配を破産手続きの中で行う必要があります。そのため、裁判所は破産管財人を選任し、時間と費用をかけて破産手続きを行います。
この場合は、住宅も早めに処分することが求められますので、比較的早い段階で自宅からの退去をしなければならないといえます。
そして、その売却が終わるまで破産手続きも続いていくことになります。
これと異なり、住宅を売却してもローンが残ってしまう場合は、この住宅は破産手続きの中では取り扱われることはありません。住宅が財産とはみなされないため、これだけで管財人が選任されることもなく、住宅が売却できなくても破産手続きは先に終了することもあります。
ですので、このような住宅があっても破産手続きが複雑化したり、長期化したりすることはありません。
また、破産手続きとは無関係に進むため、それほど急いで住宅を売却しなくてもよい場合もあり、退去まではある程度、時間の余裕があることが多いといえます。
このように、住宅ローンと破産手続きの関係は少し複雑ですが、どちらにしても退去を求められることになります。
この場合、いつごろまでに退去しなければならないのでしょうか。
実は、住宅を処分する方法は2通りあります。1つは任意売却といい、不動産業者などに買い手を探してもらい、買い手と契約して売却する方法です。
もう1つは、競売といい、住宅ローンの抵当権者が裁判所の許可を得て、裁判所での競売により買い手が決定される方法です。
任意売却での処分を行う場合は、新しい買い手に売却するころまでに退去すればよく、ある程度、柔軟に対応してもらえる場合もあります。
これに対し、競売は、裁判所がスケジュールを厳格に定めていきますので、決められた期日までに退去しなければ、強制的に追い出されてしまうこともあります。
また、任意売却を目指していても、なかなか買い手がつかないなどの事情があれば、いずれは競売にかけられてしまいます。
このように競売となった場合、競売の申し立てから、おおむね半年程度で手続きが終了しますので、それまでに退去を終える必要があります。
その期間内に、新しい引っ越し先を決めて、荷物なども運び出さなければならないということです。
なお、どうしても住宅は残したい、という方もいると思います。
その場合は、破産以外の方法で債務整理を行うしかありません。
任意整理や個人再生手続きを行えば、住宅を残すことができる可能性があります。
しかし、どちらの場合も、十分な返済余力がなければなりませんので、それも難しければやはり破産手続きを行い、住宅を処分するしかありません。
結局、破産手続きをした場合には住宅を手放すことにはなりますが、そのための手続きはこのように複雑です。
また、破産以外の手続きをとり、住宅を残す場合にも、いろいろな条件と手続きが必要となってきます。
ですので、住宅ローンの支払いができなくなった場合には、少しでも早い段階で弁護士などの専門家に相談した方が良いでしょう。
札幌の弁護士が債務整理を解説 【債務整理に関する実践的情報一覧はこちら】
【刑事事件】 刑事事件の流れ(後) ~起訴から判決まで~
札幌の弁護士による刑事事件解説コラム第2回です。
前回(刑事事件の流れ(前) ~逮捕から起訴・不起訴まで~)の続きとなります。
前回は、逮捕されてからのタイムスケジュールや、不起訴や略式命令の場合にはそこで事件が終了となること、起訴された場合には正式裁判を受けることなどを見てきました。
今回は、起訴されてしまった場合の手続きについてです。
起訴され、正式な裁判にかけられる場合にも、身柄拘束されている場合と、されていない場合とがあります。
以下では、逮捕・勾留されている場合を主に扱っていきます。
逮捕・勾留されていない場合にも、流れはほとんど同じです。
1 起訴
起訴するか、不起訴にするかの判断は、検察官が行います。
検察官が起訴を決定した場合、「起訴状」という書類を裁判所に提出し、被疑者本人にも起訴状が届くことになります。
起訴された時点で、「被疑者」という呼び名は変わり、「被告人」という呼び方をすることになります。
ニュースなどでは「被告」という言い方をすることが多いですが、実際の刑事裁判では必ず「被告人」と呼びます。
起訴後は、裁判所が裁判の日時を決め、その連絡が来ますので、その日時に裁判所で刑事裁判を受けることになります。欠席は許されません。
2 保釈
起訴された時点で身柄拘束されていない場合は、通常はそのまま自宅で生活していくことができます。
しかし、反対に、起訴された時点で逮捕・勾留されていたときは、起訴後もそのまま勾留され続けることになります。
それがいつまで続くかといえば、実は判決までそのまま拘束されてしまうのです。
札幌の場合、起訴されるまでは警察署の留置場で寝泊まりすることになりますが、起訴後、一定の時間が経過した段階で、拘置所(札幌の場合は、男性は札幌拘置支所、女性は札幌刑務支所。どちらも東区の東苗穂にあります)に移動させられます。
そこで、判決の日まで寝泊まりしなければなりません。この時点では取調べも終わってますので、裁判までの間、ただそこで過ごすだけとなります。
それでは、判決の前に釈放してもらうことは絶対にできないのでしょうか。
実は、釈放を認めてもらう方法が用意されています。それが、保釈という制度です。
ニュース等でご存じの方も多いでしょうが、保釈というのは、起訴された後、保釈金(正確には、保釈保証金といいますが)というお金を裁判所に預けることで、判決までの間、釈放を認めてもらうという制度です。
この保釈が認められ、保釈金を納めれば、身柄拘束から解放されるのです。
しかし、保釈は必ず認められるわけではありません。保釈を認めるには一定の条件があります。
保釈制度については、また後日、詳しく説明する予定ですので、ここではこの程度にしておきます。
3 公判
刑事裁判では、裁判所で裁判を行うことを「公判」と呼びます。「初公判」という言葉を聞いたことがあると思いますが、弁護士や裁判所はあまり初公判という言い方はせず、第1回公判、ということが普通だと思います。
ちなみに、民事裁判では「第1回弁論」という言い方をしており、「公判」という言葉は使いません。
第1回公判、つまり1回目の裁判は、通常、起訴から約1か月後に行われます。
公判には、被告人が出席するのは当然ですが、そのほかに、裁判官、弁護人(ベンゴニン。刑事裁判では、弁護士を弁護人と呼びます)と検察官も出席します。
そこで、裁判となっている事件について、審理を進めることになります。
実際にどのようなことを行っていくかは、また別の機会に取り上げたいと思います。
ところで、刑事裁判は、だいたい何回くらい公判を行うと思いますか?
ニュースでは、よく第5回公判とか第10回公判という話を聞きますし、1年も2年も公判が続いているような印象もあると思います。
ところが、実際の刑事裁判は、ほとんどの事件が、なんと1回目でほぼ終了しています。
第1回公判で審理がすべて終了し、その次の公判で判決を言い渡して事件が終結、というのがむしろスタンダードといえます。
ちょっと手続きが長引いても、2,3回で終結という事件が大半でしょう。そうすると、起訴から2,3か月以内には、判決が決まっていることになります。
しかも、第1回公判は、だいたい1時間以内で終了します。判決の言い渡しは5分もかかりませんので、多くの事件は、裁判全体で1時間もしないで終わっています。
ですので、裁判というのは意外とあっさり終わってしまうのです。
しかし、逆にいえば、その1時間で言いたいことをすべて裁判所に伝えなければなりませんので、それだけ事前の準備や、公判の場での活動が重要になってくるのです。
4 判決
審理がすべて終了すると、判決を言い渡す公判を開きます。
そこで、裁判官が被告人にどういう刑罰を決めるかという「判決」を言い渡します。
判決の際には、結論とその理由を述べます。
結論というのは、要するに有罪か無罪か、有罪のときはどのような刑を与えるか、というものです。
たとえば、「被告人を懲役3年に処する」というようなものです。
そして、その判決の理由として、「前科がある。内容が悪質である。反省の態度が見られない。」などの事情を説明していきます。
有罪判決には、大きく、実刑判決と執行猶予判決があります。
執行猶予判決について説明すると長くなりますので、これも別の機会に取り上げます。
執行猶予判決になればその直後に釈放されますが、実刑判決では、そのまま身柄拘束が続き、釈放してもらえません。
5 控訴・上告
判決の結論に不満がある場合には、高等裁判所に控訴することができます。
通常、刑事裁判は簡易裁判所か地方裁判所で行います(大半は地方裁判所です)。
しかし、その判決が間違っているとか、重すぎるという場合には、高等裁判所でもう一度判断しなおしてもらうことができるのです。
本当は無実なのに有罪判決を受けたとか、執行猶予をつけるべきなのに実刑判決だった、などの理由で控訴を行うことがあります。
控訴を行い、高等裁判所での判決にも不満がある場合には、最高裁判所に上告をすることもできます。
しかし、実際には上告できる場合は非常に限定されており、上告が認められることはほとんどありません。
控訴や上告をしないか、上告がしりぞけられた場合には、その判決が確定し、争うことはできなくなります。
6 刑の執行
有罪判決が確定した場合には、裁判所が命じた刑の執行を受けなければなりません。
罰金刑であれば、罰金額を納付しなければなりませんし、懲役の実刑判決であれば刑務所に服役をします。
また、裁判に関する費用の支払いを命じられることもあります。
刑の執行を終えた段階で、刑事手続きは終了といえるでしょう。
前回・今回で見てきたように、捜査開始・逮捕時から、判決を受けた後の刑の執行まで、さまざまな手続きが行われます。
要点のみにしぼって簡単に述べてきましたが、それでもかなり複雑な手続きだと思われたのではないでしょうか。
しかし、裁判が1回目で終了する場合は、逮捕から判決までの期間は、2か月程度にすぎません。
実際には、この手続きに沿ったなかで、多くの弁護活動を行っていかなければならず、時間的にも労力的にも相当大変なものとなります。
ですので、逮捕前や逮捕直後から、弁護士と相談しながら迅速に対応をしていかなければ、どんどん取り返しがつかない状況になってしまうのです。
刑事事件、刑事裁判の全体像をざっと見てきましたので、次回は、裁判ではどのようなことが行われるか、実際のケースをもとに体験したいと思います。
札幌の弁護士が刑事事件を解説 【刑事事件に関する情報一覧はこちら】
【刑事事件】 刑事事件の流れ(前) ~逮捕から起訴・不起訴まで~
札幌の弁護士による刑事事件解説コラム第1回です。
今回から、犯罪をおかしてしまったり、犯罪の疑いをかけられてしまった場合の捜査や裁判に関する手続き=刑事事件について、実際の経験などをもとにした情報を提供していきたいと思います。
なお、当事務所では刑事事件や少年事件は、主に秋山弁護士が担当しています(もちろん、赤渕弁護士と共同で行うこともあります)。
今回と次回は、刑事事件の基本的な流れについてみてきます。
刑事事件といっても、起訴されて裁判にかけられる前と、その後では、手続きの流れが全く違いますので、起訴前・起訴後の2つに分けて説明していきます。
1 任意捜査
事件が発生すると、警察は捜査を進めていき、容疑者(法律用語では被疑者といいます)を特定していきます。
被疑者が特定できたとしても、必ず逮捕するわけではなく、逮捕をしないまま事情聴取や取調べを行ったり、逮捕するための準備段階として取調べを行ったりしていきます。
このような段階では、警察も、まだ逮捕するだけの証拠がなかったり、逮捕するまでの必要性を感じていないということになります。
ですので、この段階で適切な対応を行えば、逮捕を避けられる事件もあります。
2 逮捕
ある程度の事件になると、被疑者を特定した後、一定の段階で逮捕し、身柄を拘束することになります(最後まで逮捕しない事件もあります)。
警察官が被疑者を逮捕する場合は、裁判所から逮捕状の交付を受けて逮捕を行う「通常逮捕」が主ですが、実務上は「現行犯逮捕」の例も相当多くあります。
現行犯逮捕は、事件の現場で証拠隠滅や逃亡をふせぐためにとりあえず逮捕した、という事件も実際上よく見られ、1,2日で釈放されるケースもあります。
しかし、逮捕状を取得してまで逮捕したような事件では、すぐに釈放されるというケースはあまり目にしません。そのまま身柄拘束を続けて、本格的な取調べを行っていくのが通常だと思います。
逮捕は、通常、警察官が行い、逮捕された被疑者は、警察署の留置場に入れられます。基本的にはその後の取調べも警察署内で警察官により行われますが、そうでない場合もあります。
法律上、逮捕後の身柄拘束は、実は48時間以内に限られています。それ以上の身柄拘束を行うときは、まず検察庁に事件を送致する手続きをとらなければなりません。
3 勾留
検察庁とは、検察官・検事がいる場所のことで、東京地方検察庁(東京地検)などの名前をよくニュースなどで見ると思います。札幌にも、札幌地方検察庁(札幌地検)があります。
警察から検察庁に事件が送致されると、被疑者も検察庁に連れて行かれ、検察官・検事の取り調べを受けることになります。
その取調べの結果、検察官が、身柄拘束を続ける必要があると判断した場合、裁判所に勾留の請求をします。
勾留というのは、要するに逮捕後も身柄拘束を継続するということで、逮捕後に勾留が認められると、起訴・不起訴が決定されるまでに、さらに10日間から20日間の身柄拘束ができることになります。
ですので、逮捕後の検察官の取調べなどの結果、検察官がまだ10日間の身柄拘束を続けるべきと判断したときは、勾留の請求を行います。
検察官が勾留の請求をすると、今度は被疑者は裁判所に連れて行かれ、裁判官と面談をします。
その面談を勾留質問といいますが、裁判官は、事件の内容を認めるか否認するかなどを被疑者に確認します。
そして、事件の資料などを検討し、裁判官が勾留が必要だと認めれば、勾留決定を行い、10日間の身柄拘束を決定します。
反対に、これ以上の身柄拘束は必要ないと判断すれば、勾留請求は却下され、すぐに釈放されることになります。
4 勾留期間の延長
勾留が認められてしまうと、原則として10日間、身柄拘束が続きます。
検察官は、その期間内に被疑者を起訴するかどうかを決定する必要がありますが、関係者が多い場合などは、10日間では時間が足りないという事態も生じます
そのようなとき、さらに10日以内の期間、勾留期間を延長することが認められています。
その場合、最初の勾留の際と同様に、検察官が裁判所に勾留期間の延長を申請し、裁判所が認めるかどうかを判断することになります。
なお、延長は10日以内に限り認められていますので、結局、全部で20日以内に限定されることになります。
5 処分の決定
勾留を行っている場合、勾留期間の最終日までに被疑者の処分を決定します。
処分の種類にはいくつかあり、主なものは以下のとおりです。
・起訴 被疑者を正式裁判にかけ、裁判所に有罪無罪や刑の重さを判断してもらう。
・不起訴 その事件で被疑者に処分・刑罰をくだす必要はないとして、事件を終了させる(おとがめなし)。
・略式命令 罰金刑で済む場合に、簡易な手続きで罰金額を決定して、支払いを命じて釈放させる。罰金さえ納めれば事件は終了。
・処分保留 勾留期間内に処分が決められないため、いったん釈放して捜査を継続し、後日正式に処分を決める。
このうち、不起訴はおとがめなしの判断であり、それで事件が終了となります。処分保留として釈放される場合は、すぐに別件で再逮捕されることもありますが、そうでない場合にはほとんどが不起訴で終わっています。
略式命令は、比較的軽微な事件だけど、不起訴とはできない場合に、勾留期間終了時に罰金の支払いを命じて釈放させるものです。事件自体はそこで終了し、あとは罰金を納付する手続きが残るだけになります。
これらの処分は、どれも勾留期間が終了すると同時に事件もほぼ終了となりますので(処分保留は例外もありますが)、その後に裁判が続くということはありません。
ところが、起訴という処分が下されてしまうと、正式裁判にかけられることになります。
この場合、基本的には判決が出るまで身柄拘束が継続されることになってしまい、釈放されないままとなってしまいます。
また、裁判を受けることになりますので、裁判のための準備も必要となってきます。
そのため、起訴されるか、それ以外の処分になるかによって被疑者が受ける負担は全く違うものになってしまいます。ですので、早期に釈放され、社会復帰をするためには、可能な限り起訴を避けることが必要になってくるのです。
6 スケジュールの参考例
起訴、不起訴までの流れはだいたい把握できたでしょうか。
参考として、逮捕され、20日勾留された後、不起訴で釈放となるような事件のタイムスケジュールは、次のとおりです。
7/1 逮捕
7/3 検察庁で取調べ、勾留請求される
7/4 裁判所で勾留質問、勾留が決定(7/12まで)
7/12 勾留を10日間延長することが決定(7/22まで)
7/22 不起訴の処分を得て、釈放。事件終了。
この間の期間は、取調べを受けたり、現場検証に立ち会ったりしながら進んでいきます。
なお、最初の10日間の勾留の日数があわないと感じるかもしれません。
勾留日数の数え方には特殊なルールがあり、実際には、検察官が勾留請求をした日から、その日を含めて10日以内のみ認められる、という決まりになっています。
ですので、7/3に勾留請求をすれば、その日を含めて10日間、つまり7/12までの勾留が可能となるのです。
実際には上の参考例よりも短い日数ですむ場合もありますが、この参考例のように最大限の日数身柄拘束が続くケースも少なくありません。
これだけの期間を、弁護士の手助けのないまま乗り切ることは、相当厳しいのではないでしょうか。
さて、次回は、起訴されてしまった場合のその後の流れを見て行きたいと思います。
札幌の弁護士が刑事事件を解説 【刑事事件に関する情報一覧はこちら】